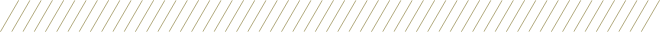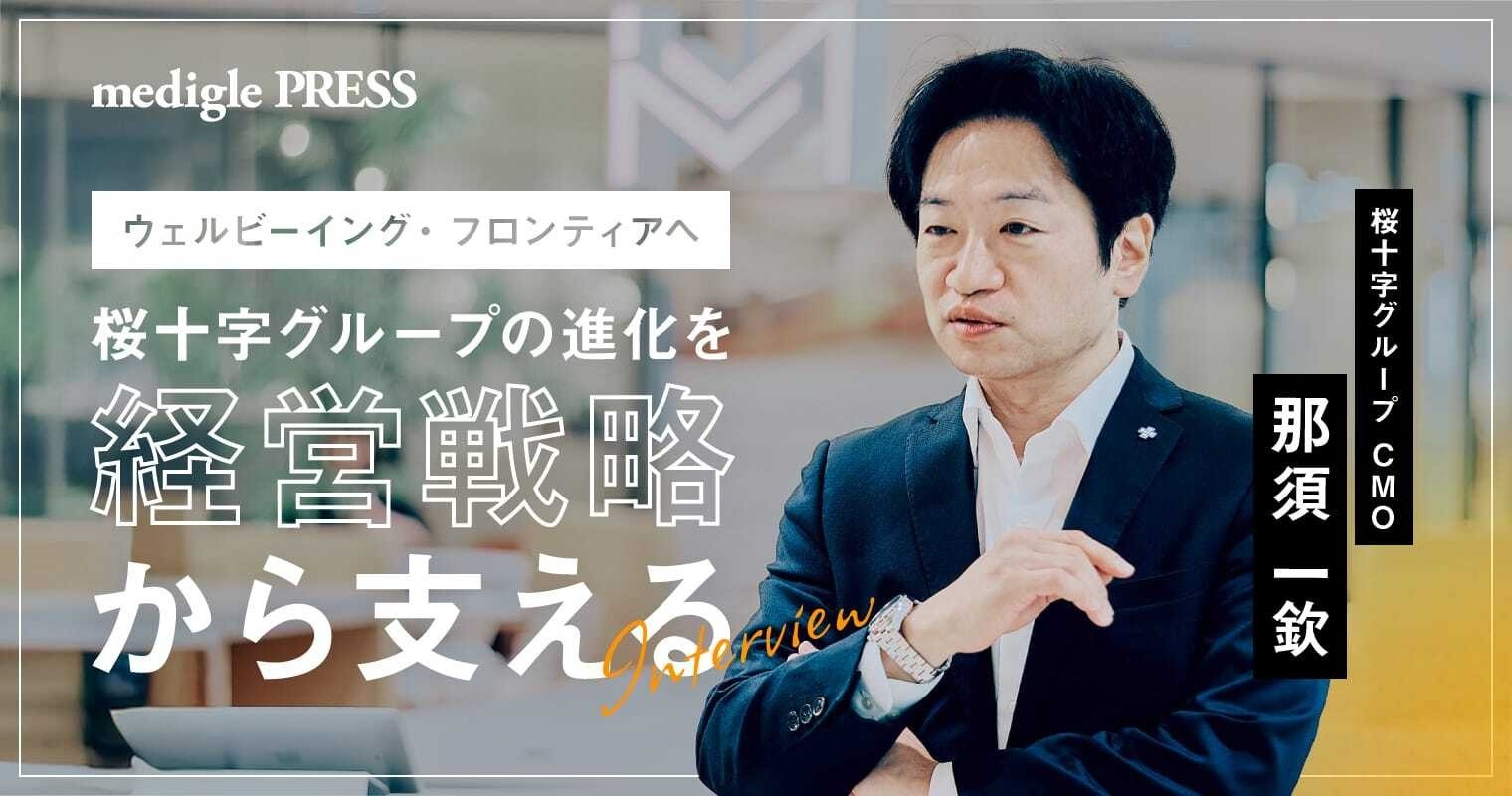大阪けいさつ病院のDX戦略 スマートホスピタルの現在地とその先へ
2025年09月29日

限られた人材、増え続ける業務量、そして多様化する医療ニーズ。医療現場が抱えるこうした構造的課題に、病院としてどう向き合うか。大阪けいさつ病院は、新病院の開院を機に、「スマートホスピタル」への本格的な移行に踏み切りました。
この取り組みの主役は、新しい機器でも革新的なアプリでもなく、現場で働く一人ひとりの職員です。2025年の新病院開設にあわせて、全職員へのiPhone一斉支給を起点に、電子化・自動化・可視化を一体的に推進。単なるデジタル導入にとどまらず、医療・看護・事務・地域連携・教育といったあらゆる領域で、現場起点の改革を進めています。
目指すのは、「業務の質」と「働きやすさ」を両立する持続可能な医療体制。その背景と展望について、病院長 澤芳樹氏と、医療情報部 山本剛氏にお話をうかがいました。
病院建て替えを好機と捉えた、DX推進の決断
澤病院長: 病院の建て替えは、単に建物を新しくするだけではありません。私たちはこれを、業務の流れや働き方といった病院運営全体を見直す絶好の機会と捉えました。ハードの刷新にとどまらず、ソフト面にも大きく踏み込んだ改革が必要だと考え、病院全体でDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する方針を掲げました。
最初のステップとして、院内の通信インフラを抜本的に見直しました。5Gを含む高速かつ安定したネットワークを整備し、全職員約1,800名にiPhoneを一斉支給。これにより、PHSを全面廃止し、ナースコール対応、電子カルテの参照、部署間連絡、スケジュール確認など、日常業務の多くをスマートフォン一つに統合しました。
このようにスマートフォンを“共通の作業環境”とすることで、職種や部署を超えてリアルタイムに情報共有が可能となり、時間的・空間的な制約が大きく緩和されました。その結果、チーム医療の連携密度も着実に向上しています。
こうした取り組みの根底にあるのは、限られた医療資源を有効活用し、持続可能な医療提供体制を築くという強い思いです。「スマートホスピタル」は流行としての導入ではなく、地域医療の中核を担う病院として、次の時代に応えるための必然的な選択だと考えています。
.png)
新病院の院内(2階外来、1階エントランス)
iPhone配布のその先へ。日常の延長にある業務改革
山本氏: iPhoneを配布しただけで業務が変わるわけではありません。私たちが目指したのは、「スマホのような直感的な使いやすさを、業務にも持ち込む」ことでした。
たとえばナースコールでは、患者ごとのベッド情報と連動して通知されるため、看護師は誰が呼び出しているかを即座に把握できます。以前は、ナースステーションに戻って確認し、再び病室へ移動するという無駄がありましたが、今では直接目的地に向かえるようになり、業務効率が大幅に改善しました。
また、職員間の連絡手段として導入したチャットアプリでは、部署間連絡が迅速に行えるだけでなく、既読確認機能やログの保存により、伝達ミスや確認漏れが減少しています。これにより、特に夜間や緊急時の対応においても、チームの機動力が高まりました。
澤病院長: 業務がシームレスにつながることによって、「次の行動への迷い」がなくなったと多くの職員が感じています。電話の取次ぎ、紙の回覧、会議資料の印刷、こうした“病院あるある”の手間が、一つずつ着実に削減されています。

「現場の声」が変革の原動力に
山本氏: 導入にあたって特に重視したのが「現場主導の開発」です。当院では、20代・30代の若手職員を中心に「医療DXチーム」を立ち上げ、実際に業務に携わるメンバーが「こうしたい」「ここが困っている」といった声をもとに、アプリやワークフローの改善を進めています。
澤病院長: こうした現場主導の改善は、業務の効率化だけでなく、職員のモチベーションにも良い影響を与えています。「自分たちが動けば、病院が変わる」という手応えを得られることで、職場全体に前向きな空気が生まれるのです。現場の声が起点となり、病院の仕組み自体が変わっていく──まさにそれが、DXの本質だと考えています。
スマートホスピタル2.0へ。生成AIと外部連携の拡張
 (1).jpg)
山本氏: いま私たちは、スマートホスピタル構想の次なる段階、いわば「2.0」フェーズへと歩みを進めています。初期フェーズではインフラ整備やiPhone配布による業務の可視化・効率化を中心に据えてきましたが、今後はさらに一歩進んで、生成AIや外部技術との連携を通じた“業務の高度化”に取り組もうとしています。
具体的には、生成AIを活用した診療録の音声入力支援、問診票の自動構造化、看護記録のテンプレート化などを導入予定です。こうした技術は、医師や看護師の記録負担を軽減し、本来注力すべき「対話」や「観察」により多くの時間を割ける環境づくりにつながると考えています。
また、当院では大阪商工会議所と連携し、外部企業との共同研究・実証プロジェクトの公募を行いました。その結果、医療機器、IT、ロボティクス、AIなど多様な分野から20件を超える提案が寄せられました。現在はその中から8件を採択し、院内でPoC(概念実証)を進めています。
取り組みの一例として、災害時に要配慮者を安全に避難させるための支援ロボット、遠隔でのリハビリ指導を可能にする支援システム、院内の医薬品や備品の在庫管理を自動化する仕組みなど、いずれも実用化を見据えた検証が進行中です。これらは、単なる“便利さ”の追求ではなく、地域の医療ニーズにどう応えるかという視点で選定しています。
澤病院長: 病院という場所を、診療や治療にとどまらず、“共創と実証のフィールド”として開放する。それは、医療の質を守り、進化させていくために私たちが果たすべき使命の一つです。多様な技術と現場の知見が交差することで、これまでにない発想や解決策が生まれる。そうした場を病院が提供する意義は非常に大きいと感じています。
地域医療連携は「マーケティング&アライアンス」
澤病院長: 大阪市内は、大学病院や基幹病院が限られたエリアに密集する非常に特殊な医療圏です。その中で当院が果たすべき役割を明確にするため、地域医療連携を「マーケティング」と「アライアンス」という2つの視点から再設計しています。
マーケティングの観点では、当院の強みである循環器、脳神経外科、整形外科といった専門領域の機能を明確に打ち出しています。地域の医療機関に対しては、症例紹介や医療連携説明会などを通じて、患者紹介の適切なタイミングや病態像を丁寧に共有。こうした発信によって、地域の先生方が「どういうときに当院へ紹介すれば良いか」を判断しやすくなる関係性を築いています。
また、アライアンスの視点では、診療所や近隣病院との役割分担と、紹介後の確実なフィードバック体制の強化を重視しています。紹介状や返書の標準化に加え、患者紹介時に必要な情報である既往歴、検査データ、服薬状況などの整理も進め、現在は一部クリニックと専用アプリを用いた情報連携も試行しています。これにより、紹介元と当院の間でリアルタイムにやり取りができる体制の構築を目指しています。
地域の中で当院がどのような機能を担うのかを明確にし、その役割を理解したうえで医療機関同士が連携する。そうした「情報設計」と「信頼構築」が、これからの地域医療連携には求められていると感じています。
データの力で医療を循環型に
澤病院長:診療記録や検査データ、看護記録、処方履歴など、医療現場には日々膨大な情報が蓄積されています。こうした医療データは、単なる記録ではなく病院にとって重要な資産です。しかし、活用されなければ、価値ある成果にはつながりません。私たちは、こうしたデータを患者ケア、教育、研究、経営などに再活用できる仕組みづくりを進めています。
その一例が、診療報酬の「見える化」です。これまで一部部門のみに共有されていた点数情報を、医師や看護師にも開示し、各業務の経済的な価値が見えるようにしています。「この処置がどれだけの点数か」「病院収支にどう貢献しているのか」を意識できることで、職員の経営的な視点や意識も育っています。
これは単に収益向上を目的とするのではなく、「自分の仕事が医療の質や病院の持続性にどうつながるのか」を実感できるようにする取り組みです。こうした可視化は、部署ごとの目標設定や業務改善の基盤にもなっています。データを単なる報告にとどめず、現場で回し、改善を生み出す。そんな循環型のデータ活用が、私たちの目指すDXの一つの形です。
“For the patient” を支える仕組みへ

澤病院長:私は心臓外科医として、多くの難症例に向き合ってきました。特に「他の医療機関で治療が困難だった患者さんを、どうにかして救いたい」という想いを強く持ち続けてきました。それが私の医療者としての信条であり、原点です。今、その精神を個人のものにとどめず、病院全体の方針や仕組みとして昇華させていくことが私の使命だと考えています。
スマートホスピタル構想も、その延長にあります。新しい技術の導入が目的ではなく、職員一人ひとりが「働きやすく、迷いなく医療に集中できる」環境をつくること。それが結果として医療の質や、患者さんの安心につながると私たちは捉えています。
“For the patient”という理念を、日々の診療や看護の中で具体的に支える構造が、これからの時代は問われるのではないでしょうか。
大阪けいさつ病院は、これからも“変化を恐れず、常に前へ進み続ける病院”でありたいと考えています。地域の患者さん、医療機関、そしてそこで働くすべての人たちとともに、未来の医療のかたちを創っていきます。
大阪けいさつ病院
2025年1月に第二大阪けいさつ病院と統合、新築移転。650床を備える高度急性期病院として再出発し、「いのち輝くスマートホスピタル」の基本方針のもと、モバイル端末と統合データベースを活用することで、診療と業務の効率化を実現している。
-
所在地
大阪市天王寺区烏ヶ辻2-6-40
-
病床数
650床(ICU28床/HCU28床/SCU9床)
-
URL
https://oim.or.jp/
こんな記事も読まれています