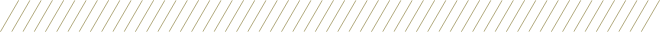Doctor's interview
NORIYUKI
KINOSHITA
武田病院
循環器センター長
/心不全センター長
患者さんにやさしい低侵襲治療と連携の力で、心不全に挑む
武田病院 循環器センター・心不全センターでは、心不全に対して薬物療法やカテーテル治療に加え、緩和ケアまで幅広く対応しています。24時間救急に備える中核病院として、不整脈治療センターや心臓血管外科、多職種チームと連携し、地域の先生方とともに切れ目のない診療を実践しています。
心不全パンデミックに備える診療体制
世界に類を見ない高齢化社会を迎える日本では、心不全に対応できる医療従事者の不足から「心不全パンデミック」が懸念されています。京都市でも高齢化が進み、心疾患の罹患率は上昇傾向にあります。当院は地域の中核病院として、この課題にしっかりと応えられる診療体制を整えてきました。
心不全は「死なない病気」とみられがちですが、日本循環器学会と日本心不全学会は「心臓が悪いために息切れやむくみが起こり、進行して生命を縮める病気」と定義しています。日本では循環器疾患による死亡数はがんに次いで第2位であり、心不全の5年生存率は約50%と大腸がんと同程度の予後とされています。

また、心不全は入退院を繰り返しながら徐々に悪化し、ご家族の負担も大きく、地域の先生方からも「対応が難しい」と伺うことがあります。当院では、救急搬送の受け入れから急性期の治療まで担い、状態が安定すればかかりつけの先生にお戻しする一方で、生命に関わる場面には24時間対応できる体制を整えています。
また、高齢の患者さんは循環器疾患に加えて他の病気を併発することも多いため、院内の各診療科と連携し包括的にサポートしています。こうした体制を基盤に、地域の先生方や看護師(慢性心不全認定看護師)・薬剤師・リハビリ・栄養士・心不全療養指導士などのコメディカルと協力し、切れ目のない心不全診療を実践しています。
心不全の背景にある基礎疾患への治療に強み
当院の大きな強みは、不整脈治療センターや心臓血管外科を併設し、心疾患に幅広く専門的に対応できる体制を有していることです。心不全の患者さんには、発症の背景に原因疾患が隠れていることが少なくありません。基礎疾患を早期に見つけて治療することで、心不全そのものを予防できる可能性があります。
さらに入院中には、栄養士による退院後の食事指導や、健康運動指導士による心臓リハビリテーションを実施し、体力の回復を支援しています。これにより、再発や重症化の予防につなげています。
中核病院として「小回りの利く柔軟さ」を生かし、地域に根差した診療を展開してきたことも、当院ならではの強みです。

不整脈を合併した心不全への積極的治療
心不全の患者さんの中には、不整脈を合併している方が少なくありません。当院では不整脈治療センターと連携し、アブレーション治療を積極的に行っています。原因となる不整脈を治療することで、心不全そのものが改善するケースもあります。
実際に、立ち仕事で足のむくみや息切れに悩み、仕事継続を諦めかけていた料理人の患者さんが来院されました。検査の結果、心房細動によって心臓の働きが低下しており、入院のうえアブレーション治療を実施しました。心左室駆出率(LVEF)は40%から60%に改善し、現在は元気に仕事に復帰されています。
また、最新のガイドラインではLVEFが40%以下で心不全を起こしやすい患者さんに対し、埋め込み型除細動器(ICD)の使用が推奨されています。

冠動脈疾患に対する低侵襲な治療
当院の循環器センターでは、動脈硬化に伴う冠動脈疾患の治療にも積極的に取り組んでいます。冠動脈の狭窄に対してはステント治療が一般的ですが、高齢者に多い石灰化病変ではステントが十分に広がらず、再狭窄を起こすことがあります。
当院では、こうした石灰化病変に対してロータブレーター治療を実施しています。先端にダイヤモンドチップを備えたドリルで病変を切削し、再狭窄を抑制します。さらに、エキシマレーザー冠動脈形成術も導入しており、レーザー光でプラークを分子レベルから蒸散させ、血栓やステント再閉塞にも対応可能です。2012年に保険適用となったエキシマレーザー治療は、京都で導入している施設はまだ限られている中、当院では深夜の急性心筋梗塞症例に対しても、迅速な対応に努めています。
また、患者さんの負担をできる限り軽くするため、細いカテーテルを用いた低侵襲の治療を心がけています。
従来の大腿動脈アプローチでは出血や穿刺部位の炎症といった合併症が多く、治療後は長時間仰向けで安静を強いられるなど、患者さんにとって大きな負担がありました。現在は遠位橈骨動脈からより細いカテーテルを挿入する方法を採用しています。術後すぐに歩行でき、圧迫による痛みも軽減されています。患者さんにとって「よりやさしい治療」を実現できていると感じています。
加えて、血管内超音波や光干渉断層法(OCT)を用いて血管病変の性状やステント展開の精度を確認し、丁寧な治療を実現しています。重症心不全患者さんには、IABPやECMOを使用しています。低侵襲で心臓の機能をサポートできる装置であり、施設認定が必要ですが、当院では他院からの依頼にも応じて治療を行っています。今後、補助循環用ポンプカテーテル「インペラ(Impella)」の導入も検討しています。

治すと支えるを同時に行う、心不全緩和ケア
当院では心不全緩和ケアにも力を入れています。緩和と聞くとがん治療を思い浮かべる方が多いですが、心不全の場合は症状を和らげながら積極的治療も並行するのが特徴です。例えば狭心症を背景に心不全が進行し胸水がたまっている場合、薬で息苦しさを軽減しつつ、必要に応じて入院のうえインターベンション治療を行います。
心不全センターでは、看護師・薬剤師・リハビリスタッフなど多職種が連携し、患者さんの思いに寄り添った緩和ケアを実践しています。日本人は「最期は自宅で家族と過ごしたい」と願う方が多い一方、医師に希望を伝えにくい現状があります。そのためカンファレンスで意向を確認し、「生き方ノート」に将来の意思決定を整理いただく取り組みも進めています。
さらに、人生会議(ACP:Advance Care Planning)を通じて「一度は自宅に帰りたい」といった希望を実現するきっかけにつなげています。すべての希望を叶えることは難しい場合もありますが、できる限り人生に寄り添う支援を重視しています。私は日本心不全学会公認プログラム「HEPT」のファシリテーターとしても活動し、緩和ケアの普及に努めています。
薬物治療と地域での見守り体制
心不全の薬物治療は2025年に大きく進歩し、現在は「ファンタスティック4」と呼ばれるβ遮断薬・アルドステロンブロッカー・ARNI(アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬)・SGLT2阻害薬の4剤が標準治療として推奨されています。当院では、血圧低下などで十分に投与できない方や服薬忘れのある方に対しても積極的に介入し、きめ細やかに調整しています。
心不全は悪化を早期に察知することが重要であり、退院時にはお薬手帳に「心不全シール」を貼付し、門前薬局でも注意して見守れるよう工夫しています。特に退院後1か月は再入院リスクが高いため、薬剤師からも患者さんに積極的な声かけをお願いし、必要に応じて主治医への受診につなげています。病院と薬局が一緒に見守ることで、悪化防止に直結しています。
さらに京都では2019年、心不全の予後改善を目的とした「京都心不全ネットワーク協議会」が発足しました。代表は京都府立医科大学 循環器内科学・腎臓内科学の的場聖明教授で、当院を含む主要病院が参加しています。共通の「心不全手帳」が導入され、かかりつけ医・病院・介護サービスがスムーズに連携できる仕組みが整いました。手帳には「目標体重に対して1週間で2キロ増えるとむくみがあり、心不全悪化が疑われる」といった具体的な目安が記載されており、患者さん自身や地域の先生方が早期に対応できる実用的なツールとなっています。
心不全患者さんを、地域とともに支えていく
当院では「地域連携の会」を定期的に開催し、心不全や不整脈治療に関する最新の知見や新しいデバイスを共有しています。診療現場で役立つ情報交換の場として、多くの先生方にご参加いただいています。
診療の実際では、ご紹介いただいた心不全の患者さんを退院後には原則としてかかりつけの先生にお戻しし、新たな心疾患が見つかった場合は内服治療をお願いする一方で、当院は定期的な心臓検査を担当するなど役割を分担しています。こうした連携を通じて、治療方針を理解いただき、信頼関係を築いていきたいと考えています。

経過については情報提供書で共有するほか、患者サポートセンターにて詳細も確認いただけます。
また、専用ホットラインを設け、当直帯を含めて24時間、日本循環器学会認定の循環器専門医が対応いたします。心不全に加え不整脈治療も強みとする当院の体制を、ぜひご活用ください。

医療法人財団 康生会 武田病院
1970年の開設以来、救急救命医療に力を注ぎ、心臓血管外科・循環器内科・脳神経外科・内科・外科が連携して24時間体制で対応。 先進的な取り組みを重ねながら、患者さんとご家族への「思いやりの心」を忘れず、理想の医療を追求し続けている。
-
所在地
〒600-8558 京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町841-5
-
病床数
374床
-
URL
https://www.takedahp.or.jp/koseikai/