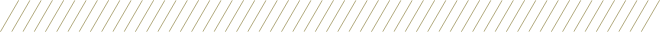地域医療連携推進法人HAMA設立
地域医療の未来を拓く
浜松アカデミック・メディカル・アライアンス(略称:HAMA)が、浜松医科大学と浜松医療センターの連携を担う組織として2025年に設立されました。
診療・教育・研究・災害対応といった幅広い分野で力を合わせ、地域に安心と信頼を届ける体制づくりを進めています。
半世紀の協定が生んだ必然の一歩
今野理事長:HAMA設立の背景には、浜松医科大学(以下、浜松医大)と浜松市の長年のつながりがあります。
1974年、浜松医大創立時に初代学長が浜松市長と臨床教育実習の協定を締結。以降、市長を開設者とする浜松医療センター(以下、医療センター)と教育面での連携を継続してきました。2017年には浜松市と浜松医大が包括連携協定を締結し、連携が加速。同年に制度化された地域医療連携推進法人の枠組みを活用し、機能分担と業務連携を深め、地域住民へ質の高い医療を効率的に提供していきます。
海野院長:浜松医大と医療センターは、これまでも緊密な連携を続けてまいりました。当院には、浜松医大の医局で研鑽を積んだ多くの医師が在籍し、日々診療に従事しています。今回の法人設立により、両施設の絆はいっそう強固なものとなり、より自然な形で連携が深化していくことが期待されます。

竹内病院長:浜松医大は静岡県で医師、看護師を養成する唯一の医科大学で、特定機能病院として先進的な医療を提供する責務も担っています。また、大学病院として新しいエビデンスを地域・世界へ発信する使命があります。教育・医療・研究の各面で、HAMA設立は大きな前進です。教育面では、学生が規模の大きい市中病院である医療センターで臨床実習を行うことで、大学病院では出会いにくい症例も経験できます。研究面では、両病院を合わせて約1,200床という規模を活かし、大規模臨床試験も可能になると期待しています。

HAMAの名称に込めた「アカデミック」の意義
今野理事長:地域医療連携推進法人「浜松アカデミック・メディカル・アライアンス(Hamamatsu Academic Medical Alliance、略称:HAMA)」は、私の長年の構想が形になったものです。名称については海野院長が提案されました。全国に50を超える地域医療連携推進法人がありますが、「アカデミック」を冠しているのはHAMAだけです。
当初、私は「アカデミック」を入れると名称として長すぎるのではと思いましたが、海野院長は教育を正面に掲げるべきだという強い思いを持っておられました。振り返れば、内科学の泰斗である吉利和 初代学長は、学部教育を充実するために、当時の平山博三 浜松市長と協定を結びました。半世紀を経た今、法人の名称に「アカデミック」が加わったことは、その歴史的な意思が受け継がれ、現在の医療へとつながっている証だと感じています。
海野院長:国立大学法人が地域医療連携推進法人を設立するのは、全国でも初めての試みであり、当初は文部科学省の対応も不透明な状況でした。そのため綿密な調整を重ねた結果、大学の正式な参加が実現しました。名称には、教育の重要性を示す意味を込めて「アカデミック」という言葉を採用し、「ハママツ アカデミック メディカル アライアンス」としました。また、「アライアンス」という響きの良さに加え、略称“HAMA(ハマ)”が自然に浜松を想起させることから、この名称を選定しています。
HAMAが実現する、高度医療の効率的な提供
今野理事長:今後は病院の集約化が進む中で、HAMAが地域の高度急性期医療を担う核となると考えています。両医療機関で人材育成や高度医療を進める中で、それぞれの課題も明らかになってきました。高度な技術を持つ医師が両医療機関で治療を行うといった交流により、地域全体として医療レベルの向上が期待されます。
竹内病院長:例えば、一方の外科で難易度の高い術式を導入する際に、もう一方の病院がその術式をすでに導入している場合は、手術だけでなく術後管理も含めて2施設で協力して行うことも可能になります。両病院が強みを活かして協力することで、安全で質の高い治療を効率的に提供できるでしょう。
海野院長:浜松医大と医療センターのICUはネットワークで結ばれ、集中治療専門医が患者情報をリアルタイムに共有し、意見交換できる体制を整えています。これにより、診療科の枠を越えて治療方針を両院で検討したり、難症例に対して助言を求めたりすることが可能となります。
将来的には、HAMAの枠組みの中で電子カルテの統合を進め、双方の病院から同じ患者情報にアクセスし、より的確な治療方針を導き出す取り組みを視野に入れています。さらに、医師だけでなく、看護師・薬剤師・放射線技師・検査技師といった多職種が交流し協働することで、相乗効果が生まれ、「1+1が2以上」の成果につながることが期待されます。
こうした連携は、地域の先生方にとっても大きな安心につながります。ご紹介いただいた患者さんの診療や情報共有が一層円滑になり、重症例にも確実に対応できる体制が整うことで、安心して患者さんを託していただける環境が広がっていきます。

ジェネラリストとスペシャリストを育成する教育
今野理事長:半世紀前の協定は学部教育に関する内容ですが、いま求められているのは卒前・卒後教育の充実です。現在卒後教育における柱の一つである総合診療医のように幅広く診られるジェネラリストと、竹内先生の専門である食道外科や肝胆膵外科のように高度な技術を持つスペシャリストをどのように育成するかが喫緊の課題です。これまで多くの卒後教育プログラムは専門医育成が中心でしたが、現実の医療との乖離が問題となっています。両者に共通する教育と両者をバランスよく育成することが大切で、HAMAでは2つの病院が議論を重ねながら、このような卒後教育を一層強化していきます。
海野院長:全国的に外科医、特に消化器外科医の不足は深刻であり、学会からは「絶滅危惧種」とまで表現されています。2040年には外科医の数が半減し、がん手術に携わる人材が不足すると予測されています。だからこそ、若い世代に「外科は大きなやりがいと達成感のある仕事である」としっかり伝えていくことが重要だと考えています。
一方、浜松医療センターには年間6,000台を超える救急車が搬送されますが、そのすべてが高度な医療を必要とするわけではありません。総合診療医は、日常的に多く見られる病気(コモンディジーズ)や救急現場でのトリアージにおいて大きな役割を担っています。しかし、日本では海外に比べて総合診療医の育成が遅れているのが現状です。HAMAの取り組みを通じ、外科医療だけでなく総合診療分野においても地域に貢献し、人材育成を進めてまいりたいと考えています。
竹内病院長:総合診療医の育成は、大学病院が弱みとする領域です。だからこそ、医療センターの力を借り、総合診療医を志す学生が学ぶ場を提供できればと考えています。
HAMAの連携が支える、持続可能な地域医療
今野理事長:HAMAの業務の柱の一つに「病院経営の安定化」があります。これは地域医療を持続的に守るうえで非常に重要な課題です。その取り組みの一環として、医療機器や薬剤の共同購入により経費削減を図ります。すでに浜松医大・医療センター・HAMAの3者で2025年4月に覚書を締結しており、両院の事務方で構成されるワーキンググループがメーカーやディーラーとの共同交渉を本格的に進めていきます。
海野院長:医薬品に加え、カテーテルやマスクといった日常的に使用する医療材料を共同で購入することができれば、病院経営への改善に大きく貢献します。さらに、医療用ロボットや放射線治療装置といった高額な医療機器を両病院で計画的に配置することで、地域に必要とされる高度医療を効率的に提供することが可能となります。加えて、専門的な機器を管理する技師を共同で育成することにより、より確実に高度医療を実践できる体制を整えることができると考えています。
竹内病院長:全国的に病院経営は厳しく、それぞれの病院が単独で存続していくのは難しい状況にあります。HAMAによって、2病院があわせて約1,200床規模というスケールを持つことで、共同購入・人員配置・情報共有のメリットを活かし、経営を安定させていきたいと考えています。私たち3人は外科医ですが、外科医の担い手が減っていることも現実です。疾患の集約化など機能分化を進めることで、人材をより効率的に配置し、地域医療全体を持続可能なものにしていく必要があります。
災害・緊急時に備える確かな連携
今野理事長:浜松医大と医療センターはこれまでも、災害時にDMATをはじめ医師や看護師を派遣してきました。南海トラフ巨大地震は今後30年以内に約80%の確率で発生すると予測されています。HAMAで結ばれた2つの病院は立地が異なるため、平時には距離の面で不便なこともありますが、災害時にどちらかが機能停止した場合、もう一方が代替できるという強みになります。
竹内病院長:コロナ禍では、浜松市の基幹病院や後方支援病院、さらに開業医も含めて病院長が連携に努めましたが、実際には困難な点も多くありました。今後はHAMAが地域の核となり、中小病院を含むネットワークを築くことで、大規模災害や感染症に対応できる枠組みを整えていきたいと考えています。
海野院長:コロナ禍では、浜松医大のDMAT隊員が横浜港のダイヤモンド・プリンセス号に駆けつけ、その後、一部の乗客が医療センターへ搬送されました。未知の感染症への対応は、一つの病院だけで対応できるものではなく、病院間や行政との緊密な連携が不可欠です。実際、当時は静岡県病院協会を通じ、県内の病院長が頻繁にウェブ会議を開き、情報を共有しながら協力体制を築きました。
この経験を踏まえ、今後は浜松医大と医療センターが西部地域の中核となり、静岡県全体の感染症対策をリードできる体制を整えていきたいと考えています。
医工連携をはじめ、共同研究や人事交流を推進
今野理事長:文部科学省との調整後、最終的には担当官から「注目していますから、ぜひ頑張ってください」と励ましをいただきました。厚生労働省も県を通じて注視していることを知り、責任の重さを実感しています。国立大学と浜松市医療公社という公的機関同士で親和性は高いものの、やはり「文化」の違いは存在します。それを丁寧にすり合わせながら進めていくことが重要だと考えています。幸い、両病院のトップがHAMAの必要性を強く認識しており、連携は「面白い」と職員に感じてもらえれば、自然に浸透していくと考えています。細部を詰めながら、徐々に、無理のない形で歩みを進めることを大切にしています。研究については、渡邉裕司学長が臨床研究の推進を掲げておられることもあり、竹内院長・海野院長という臨床研究に精通したリーダーの下で、大きな発展が期待できると考えています。
海野院長:浜松医大は、これまで静岡大学の工学部や情報学部と連携し、医工学分野で様々な研究に取り組んできました。浜松市も医工連携を積極的に推進しており、HAMAを通じてその取り組みはさらに発展していくと期待されます。加えて、浜松医大が強みを持つ光産業分野の研究に対し、医療センターとしても積極的に参画し、地域から新しい医療の可能性を切り拓いていきたいと考えています。
竹内病院長:市民公開講座や地域の開業医の先生方を対象としたセミナー、さらには各種イベントを両病院で共同開催することも可能です。人事交流とあわせて取り組むことで、親和性の高い病院同士が互いの文化の違いを前向きに活かし、地域に還元できると考えています。

浜松から全国へ – HAMAから医療に未来の光を
海野院長:医療センターは、前身である浜松市医師会中央病院の時代から浜松市医師会との深い結びつきを持ち続けてきました。現在も、入院患者さんの約9割は地域の診療所の先生方からのご紹介によるものであり、まさに地域医療の中核を担っています。HAMAの枠組みを通じ、これまで以上に信頼される体制を築いていきたいと考えています。
近年、浜松医大の存在感は一層高まっており、浜松市医師会長、静岡県医師会長、さらには日本医師会長も同大学の卒業生です。こうした強固なネットワークと連携のもと、医療センターも地域に根ざした基盤をさらに強めてまいります。
竹内病院長:医療には厳しい現実も多くありますが、私たちは新しいことに挑戦する気概を持ち、浜松から静岡県、さらには全国へと「面白いことを実現している」と示していきたいと考えています。HAMAが暗くなりがちな医療の世界に明るい光をもたらす存在となれるよう、力を尽くしていきます。
今野理事長:現在、病院は厳しい環境に置かれています。しかし、そのような状況でも医療者を志す若い世代が数多くいることは大きな希望であり、彼らに自らの夢を実現して頂きたいと思っています。HAMAを通して、浜松から全国へ向けて医療の新しい可能性を発信し、地域の新たなモデルを目指します。地域の先生方には、引き続きご協力とご支援を心よりお願い申し上げます。

浜松医療センター
静岡県西部地区を診療圏とする高度総合医療機関であり、地域医療支援病院、災害拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、地域周産母子医療センター、アレルギー疾患医療拠点病院、日本脳卒中学会一次脳卒中センター、そしてゲノム医療連携病院の責を担っている。
-
所在地
静岡県浜松市中央区富塚町328
-
病床数
606床
-
URL
https://www.hmedc.or.jp/