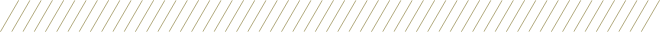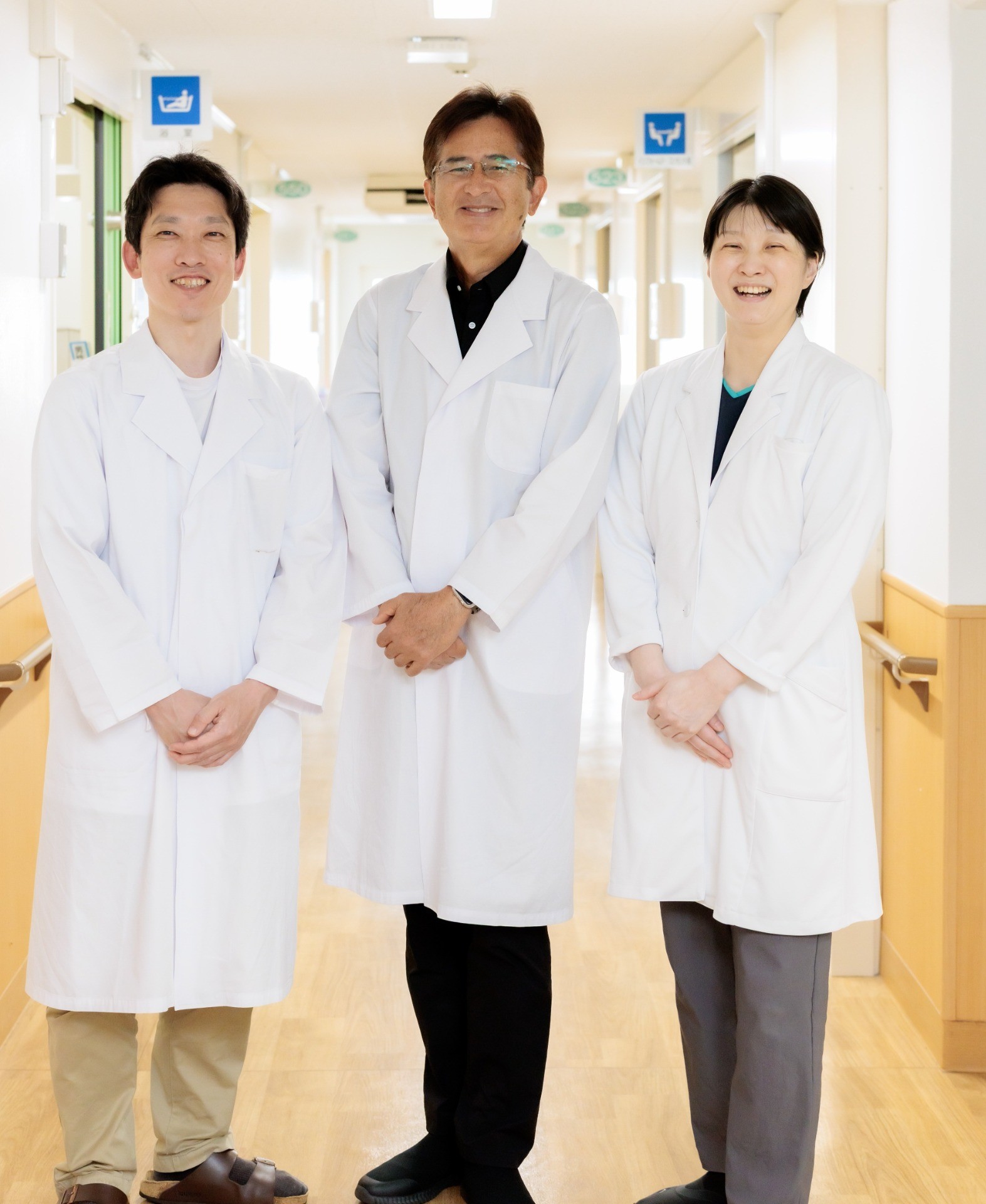新体制始動 患者さんの声を大切に、専門的な整形外科治療で地域に貢献
武田総合病院 整形外科では、骨折などの外傷から慢性疾患まで、整形外科領域全般に幅広く対応しています。2次救急病院としての役割を担いながら、大学病院で研鑽を積んだ医師たちが、それぞれの専門分野を活かした診療を行っています。武田グループや大学との連携を活かしながら、地域の医療機関とともに、地域医療への貢献を目指しています。
専門分野を生かし、堅実で幅広い整形外科治療を提供
大塚医師:2025年度より、武田総合病院 整形外科に顧問として赴任しました。京都府立医科大学卒業後、同大学院やハーバード大学で研究を行い、これまで複数の医療機関で整形外科部長を務めてきました。
整形外科の疾患は外傷、関節疾患、脊椎疾患、骨軟部腫瘍、神経障害など多岐にわたり、各分野での専門的な治療が求められます。近年は特に人工関節をはじめとする技術が急速に進化しています。
私は前任の康生会武田病院では、副院長兼手術部長として数多くの手術症例に取り組んできました。当院でも新しい技術を積極的に取り入れ、整形外科の治療に広く対応していきたいと考えています。
股関節の専門性を軸に、術式選択も柔軟に対応
後藤医師:これまで股関節疾患を専門としながら、外傷や人工関節手術を含む整形外科全般の診療に携わってきました。変形性関節症といった慢性疾患に対する人工関節の症例にも幅広く取り組んできました。股関節疾患を多く扱ってきましたので、非常に頻度の多い大腿骨近位部骨折の治療に生かせるのではないかと考えています。
大学では、大腿骨骨頭壊死に関する研究を中心に行っており、腎移植後に使用される免疫抑制剤の投与量と骨頭壊死発生リスクとの関係について解析しました。骨頭壊死は、ステロイドやアルコール摂取が発症リスクとなることが知られており、疾患理解や予防の一助となるよう努めています。

人工股関置換術では前方系のアプローチと後方アプローチの選択が可能で、それぞれの特徴をふまえて用います。前方系では、筋肉や腱の温存により脱臼リスクが低い一方で、大腿骨トラブルが多いとされています。患者さんの可動域や生活スタイルなどを考慮し、適切な方法を選んでいます。
人工股間関節手術ではインプラントの設置精度の向上を目的に簡易ナビゲーションシステムを導入しています。簡便に使用可能できるシステムは、人工関節の設置角度をより正確にコントロールでき、以前よりも正確にインプラントを設置できます。今後も、技術の進歩を取り入れながら、患者さん一人ひとりに適切な治療を提供してまいります。
また、転位型の大腿骨頚部骨折では人工大腿骨頭置換術を行いますが、インプラントの固定方法はセメントレス、セメント固定の方法があります。大腿骨近位部骨折は骨脆弱性を基盤として発生することが多く、術中骨折や術後のインプラント周囲骨折予防にはセメント固定が有利とされており、高齢者の人工大腿骨頭置換術では多くの症例にセメント固定を用いております。
肩関節と外傷に対応、地域との連携で確かな診療を
近藤医師:私は肩関節を専門として診療を行っており、これまで外傷の患者さんが多く搬送される病院で経験を積んできました。当院は2次救急を担っており、転倒による股関節・上肢・下肢・肩の骨折など、一般的な外傷に幅広く対応しています。常に患者さん一人ひとりと丁寧に向き合い、堅実で誠実な治療を心がけています。
地域の医療機関からは、手術が必要な症例はもちろん、診断に迷われるような症例のご紹介も多くいただいております。レントゲンで判別可能なケースに加え、MRI検査を行うことで、靭帯や腱、神経といった軟部組織の状態を確認でき、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症といった疾患の診断にもつながります。今後も、地域の先生方と連携しながら、確かな診療を提供してまいります。

早期診断と適切な治療で、患者さんのQOL向上に寄与
後藤医師:診療ではまず患者さんの話を聞き、病歴と局所所見をもと、画像検査を行います。手根骨や足根骨など小さな骨が多い部位で単純X線写真では骨折などの診断が困難な部位にはCTを施行します。また、骨折が疑わしいがX線写真では骨折を認めない症例や、手術症例での術前計画にもCTを行います。また、靭帯損傷や不全骨折や疲労骨折、腫瘍性病変を疑う場合にはMRIで精査します。
地域の整形外科の先生から、MRIやCT検査のみをご依頼いただくケースも多く、かかりつけ医制度のもとで、検査から治療までを含めた連携を今後さらに強化していきたいと考えています。
また、運動療法や薬物療法では症状の改善が難しく、手術を検討される患者さんもご紹介いただいております。慢性疾患の場合、手術の必要性は患者さんの生活スタイルやニーズによって異なりますので、患者さん側の求めるものを的確に把握し、それを満たすような治療方針を提示したいと考えております。外傷では治療方針が慢性疾患に比べると明確ではありますが、患者さんの背景を十分に考慮しながら、治療法を選択するように心がけています。
医師と患者の“対話”が信頼と安心につながる
大塚医師:手術や治療の成功はもちろん重要ですが、それ以上に大切なのは、患者さんと医師との信頼関係だと考えています。治療結果に問題がなくても、意思疎通が不十分であれば、患者さんの不安や不満につながる可能性もあります。日々の診療では患者さんの気持ちに寄り添いながら、納得いただける説明と丁寧なコミュニケーションを心がけています。

後藤医師:患者さんは何らかの不調や不安を抱えて受診されており、医師としてその声にきちんと耳を傾ける姿勢が不可欠と考えます。医師と患者さん側では、現状に対する認識や治療に対して期待するものが異なることも少なくありません。特に慢性疾患の場合は「現在の患者さん自身の状況とそれに対する認識、治療にどのようなものを求め、術後にどのような生活を送りたいのか」ということが治療方針に大きく影響します。そうした点をよく伺いながら、一人ひとりに合った医療を提供できるよう努めています。
グループ病院・大学と連携し、診療体制をさらに強化
大塚医師:当院にはリハビリテーション科と回復期リハビリテーション病棟を併設しており、術後も一貫してリハビリを行える体制が整っています。今後は、リハビリ部門との連携をさらに深めることで、より質の高い周術期支援体制を構築してまいります。
万が一ベッドに空きがない場合は、グループ内の「十条武田リハビリテーション病院」へのご紹介も可能です。患者さんの回復をしっかりと支えられるよう、グループ全体で連携体制を強化しています。
武田グループには、当院のほかにも康生会武田病院、宇治武田病院、十条武田リハビリテーション病院といった主要施設があり、いずれの病院においても充実した整形外科受診を行っています。このネットワークを活用することで、ほとんどの整形外科疾患に対応できる体制が整っています。さらに、京都府立医科大学附属病院とも連携し、専門的な疾患への対応や人材交流を通じて診療の質の向上を図っています。
後藤医師:今後は多くの症例に対応できる診療体制を整えたいと考えております。地域の先生方からのご紹介やご相談に真摯に対応し、患者さんにとって適切な医療を提供できるよう尽力してまいります。今後も、地域の医療機関との連携を大切にしながら、地域全体の医療の質向上に貢献して参りたいと考えています。
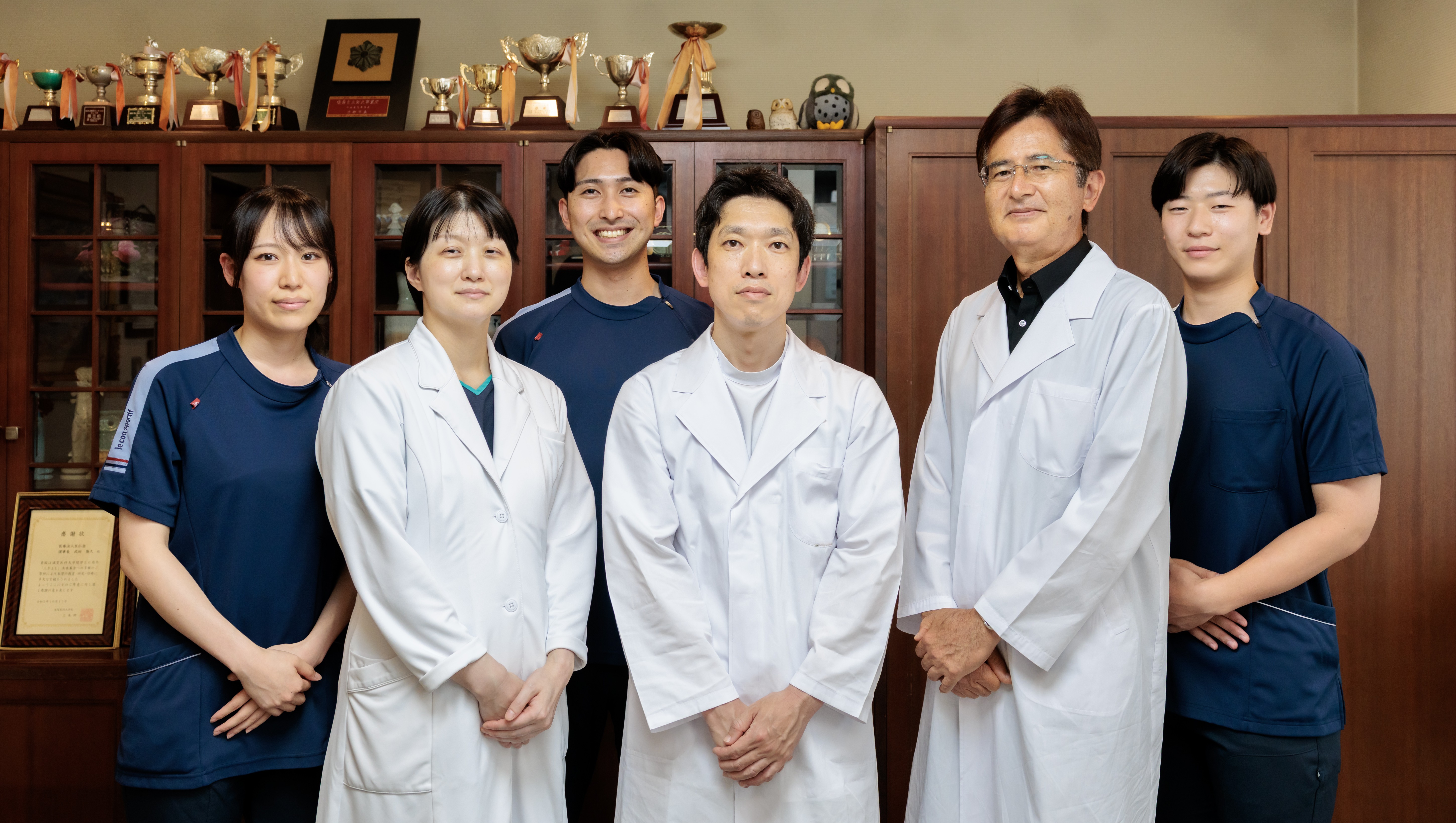
医療法人 医仁会 武田総合病院
「地域医療支援病院」として、高度医療を核に、総合的な診療体制を確立。 地域の健康文化の発信基地として、人々のからだと心のケアを支える。
-
所在地
〒601-1495 京都市伏見区石田森南町28-1
-
病床数
490床
-
URL
https://www.takedahp.or.jp/ijinkai/