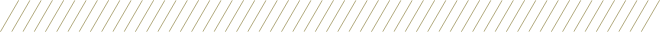Doctor's interview
HIDEYO
MIYAZAKI
国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター
病院長
平時は最善の総合診療を提供、有事には健康危機にも対応
国立国際医療研究センター病院は、国立国際医療研究センター(NCGM)の事業部門の一つとして活動してまいりました。今回、国立感染症研究所と統合され、国立健康危機管理研究機構(JIHS、ジース)としてスタートするのに伴い、「国立国際医療研究センター病院」は「国立国際医療センター」と名称を変更いたしました。
よって、当院の正式名称は、国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センターと長い名前になりましたが、今まで通り「医療センター」、「国立国際」、「NCGM」などと呼んでいただければ幸いです。ちなみに病院の英語名はNational Center for Global Health and Medicine(NCGM)となります。
新機構のロゴは、NCGMのロゴからJIHSのロゴへと変更されましたが、NCGMのロゴ自体は当院のロゴとして継続的に使用していくことになりました。引き続きよろしくお願い申し上げます。また新機構および病院のホームページについては今後もっと見やすくなるように改変していく予定です。

組織は拡大、医療・研究・国際協力を横断的に連携
JIHSには、臨床・研究・教育・国際協力など多岐にわたる機関が統合されました。臨床分野では、当院と国立国府台医療センターの2病院、研究分野では国立感染症研究所、国立国際医療研究所、さらに臨床研究センターが機能を担います。人材育成・国際協力の分野では、国際医療協力局と国立看護大学校が関わり、DMAT(災害派遣医療チーム)事務局も加わりました。
新しい枠組みの中で、当院は特定機能病院としての使命を果たし、社会に貢献してまいります。
「いつも」と「もしも」の両方に応える医療
当院では、平時には幅広い疾患に対応する総合診療を提供しながら、有事には感染症の拡大や災害などに即応できる柔軟な対応力を備えています。感染症、救急、集中治療、災害医療の分野で、日頃から備えを重ね、突発的な健康危機にも対応可能です。
また、年間1万件以上の救急搬送を受け入れる救命救急センターを中心に、国際感染症センターや糖尿病総合診療センター、エイズ治療・研究開発センター、国際リンパ浮腫センターなど、特色ある診療部門がそろっています。さらに、ハイブリッド手術室による先端手術や、希少疾患である腹膜偽粘液腫への高度治療も行っています。

がん・国際診療など多彩な専門領域にも注力
がん診療にも力を入れており、地域がん診療連携拠点病院として、手術支援ロボット「ダビンチSi」を2台活用した低侵襲手術を実施。がん総合診療センターでは、ゲノム医療、外来化学療法、緩和ケア、AYA世代(思春期・若年成人)への支援など、多面的な取り組みを展開しています。
また、国際診療部を設け、外国人患者の診療にも積極的に取り組んでいます。JMIP(外国人患者受け入れ医療機関認証制度)の認証も取得しており、多言語・多文化への対応力を備えた医療提供を行っています。
研究と臨床をつなぐ、未来志向の医療づくり
当院は、研究所や臨床研究センター、国際医療協力局との連携により、国際水準の臨床研究や医師主導の治験を推進しています。臨床現場と研究が密接に結びつくことで、エビデンスに基づいた新しい医療を創出し続けています。
私たちは、「高度急性期医療と研究機能を両立させる総合病院」として、地域と全国の皆さまの健康を支え続けます。今後とも、連携医の先生方や医療関係者の皆さまのご支援を、どうぞよろしくお願いいたします。

国立国際医療センター
高度急性期医療と先進研究を担う特定機能病院。救急・感染症・がん・国際診療など幅広く強みを持つ。 2025年4月1日、国立国際医療研究センターと国立感染症研究所が統合し、「国立健康危機管理研究機構(JIHS)」が設立。
-
所在地
東京都新宿区戸山1-21-1
-
病床数
716床
-
URL
https://www.hosp.jihs.go.jp/index.html