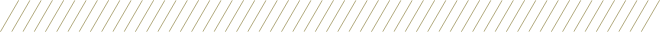Doctor's interview
NORIHIRO
KOKUDO
国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター
理事長
国立健康危機管理研究機構「JIHS」発足。
感染症対策と医療研究の新たな司令塔へ
2025年4月1日、「国立健康危機管理研究機構(JIHS:Japan Institute for Health Security)」が新たに設立されました。JIHSは、これまで感染症研究の最前線を担ってきた国立感染症研究所(感染研)と、国際医療をリードしてきた国立国際医療研究センター(NCGM)が統合して生まれた組織です。
JIHSの使命は、「感染症やさまざまな疾患に関する調査・研究や医療提供を通じて、安心できる社会の実現に貢献する」ことです。世界トップレベルの感染症対策をけん引する『感染症総合サイエンスセンター』を目指し、基礎から臨床、疫学、公衆衛生まで、幅広い分野を横断的に結びつけて研究・医療を進めていきます。また、JIHSの二つの総合病院はこれまで以上に高度先進医療を推進するとともに地域医療にも貢献いたします。
長い歴史がつながり、今へ
JIHSの背景には、日本の医療や感染症対策の歴史を築いてきた2つの組織の歩みがあります。
旧感染研のルーツは、1892年、北里柴三郎博士が創設した「私立衛生会附属伝染病研究所」です。彼はドイツで細菌学の大家コッホに師事し、破傷風菌の純粋培養やペスト菌の発見など、世界的な功績をあげました。私立衛生会附属伝染病研究所は伝染病研究所(伝研)、国立予防衛生研究所(予研)を経て、1997年に国立感染症研究所となりました。伝染病研究所には、梅毒スピロヘータの純粋培養に成功した野口英世先生、赤痢菌を発見した志賀潔先生が入所しています。
一方の旧NCGMは、1868年の戊辰戦争で設置された「兵隊仮病院」に始まり、東京陸軍病院、国立東京第一病院を経て、1993年に国立国際医療センター、2008年に国立国際医療研究センターとして生まれ変わりました。旧NCGMの名誉総裁には森林太郎(鷗外)先生がいます。
近代医学の礎を築いた偉人たちの足跡が、今のJIHSに受け継がれています。

JIHSに統合された組織の変遷
JIHS(国立感染症研究センター)には、旧NCGM(国立国際医療研究センター)をはじめ、以下の組織が統合されています。
旧国府台病院
1872年に創設された日本初期の軍病院を起源とし、戦後は国立国府台病院として精神・神経医療を担ってきました。
2008年にNCGMの一部として再編。
旧国立療養所中野病院
1920年、結核療養所として開設され、1993年に閉院し、国立国際医療センターに統合されました。
旧ハンセン病研究センター
1955年に「国立らい研究所」として設立され、1997年に旧感染症研究所に統合。
国立看護大学校
戦後の看護教育機関を前身とし、2001年に開学。卒業生の多くがナショナルセンターに就職しています。
旧予研・村山分室
1961年にワクチン検定・試験製造のため設立。1981年には、日本初のBSL4(最高度安全実験施設)が整備されました。
DMAT事務局
2005年に厚生労働省が設置した災害派遣医療チーム(DMAT)の事務局も、現在はJIHSに統合されています。
コロナ禍を経て生まれた組織
JIHSの構想が始まったのは、まさに新型コロナウイルスが猛威をふるっていた2020年です。感染症パンデミックへの国家レベルの対応を見直す必要性が高まり、2023年には法律が成立。ついに2025年、組織の形として結実しました。
JIHSの組織としては、事業部門に国立感染症研究所と国立国際医療研究所の2つの研究所、国立国際医療研究センターと国立国府台医療センターの2つの病院、国立看護大学校、臨床研究センター、国際医療協力局、さらに事業部門を支える統括部門の体制です。
JIHSの4つの柱
JIHSの主な機能は、感染症情報の収集と分析、研究開発と臨床試験、高度で総合的な医療提供、人材育成と国際連携の4つです。
1.感染症情報の収集と分析
旧感染研に早い時期から発足していた緊急時対応センター(EOC)が、平時・有事を問わず、世界中から感染症に関する情報を収集・分析します。JIHSには、感染症の発生や病原体と感染症、社会的インパクト、研究開発に関する情報を集めて分析と評価を行い、政府や厚労省、関係各省に提供して、政策決定に利用していただく役割があります。
2.研究開発と臨床試験
JIHSはリスクを評価して重点感染症を指定し、基礎研究から応用、開発の研究基盤を整備し、薬事承認まで一気通貫で貢献できる組織を目指しています。
旧NCGMは、コロナ禍で臨床情報を収集するデータベース事業COVIREGI-JPを立ち上げ、旧感染研と共同で新興・再興感染症データバンク事業(REBIND)に発展させました。REBIND事業は、2024年に発足した感染症臨床研究ネットワーク事業(iCROWN)で引き継いでいます。iCROWNの特徴は、電子カルテの情報をできるだけ自動的に集めて、有事の際に研究開発が迅速にできるネットワークづくりです。
3.高度で総合的な医療提供
JIHS 国立国際医療センターは43の診療科、716床の総合病院で、年間に約11,000件の救急搬送を受け入れ、救急医療にも力を入れています。JIHS 国立国府台医療センターは20の診療科、417床を有し、精神科と児童精神科の病床が多いのが特徴です。
JIHSは、合併症がある新型コロナウイルス感染症の重症患者の治療で必要とされた、総合病院機能を強化する方針です。

4.人材育成と国際連携
JIHSでは、旧組織時代から人材育成に力を入れており、全国の医師を対象とした「NCGM感染症専門医フェロー」では22名が研修を修了、「FETP(実地疫学専門家育成プログラム)」では128名が現場対応力を養い、新型コロナ対応でも活躍しました。「IDES(感染症危機管理専門家育成プログラム)」では、WHOやCDCなど国際機関でも研修を行い、約30名の医師が修了しています。
最近では、厚労省委託の「IDCL(感染症危機管理リーダーシップ研修)」を開始し、地域の行政官の育成にも取り組んでいます。また、災害医療を担うDMATの事務局もJIHSに移管され、感染症や災害など広範な緊急対応体制を整備しています。
国際連携では、J-GRID+を2024年に始動し、日本の大学10校と海外11拠点とで研究協力体制を構築。アジア各国にARISEネットワークの連携拠点を整備し、PMDAや国立がん研究センターと連携した地域ネットワークも準備中です。 さらに、JICAとの連携や7つあるWHO協力センターの機能も引き継ぎ、国際医療協力の活動を継続して参ります。
「1+1」が「2以上」になるような組織を目指して
JIHSは、単なる組織の統合ではありません。主に2つの旧組織から成り立ちますが、これまで別々のフィールドで活躍してきた知見や人材を融合し、1足す1が2以上となる相乗効果(シナジー)を生み出すことを目指しています。コロナ禍では十分にできなかった役割も、JIHSのもとでよりスムーズに力強く担い、さらにプラスアルファを生み出したいと思います。
JIHSは、信条のように「常に世界的な視野で、強くしなやかに、革新的に、公正かつ誠実に、高度な専門性に基づき」職務を果たし、歩みを進めてまいります。

国立国際医療センター
高度急性期医療と先進研究を担う特定機能病院。救急・感染症・がん・国際診療など幅広く強みを持つ。 2025年4月1日、国立国際医療研究センターと国立感染症研究所が統合し、「国立健康危機管理研究機構(JIHS)」が設立。
-
所在地
東京都新宿区戸山1-21-1
-
病床数
716床
-
URL
https://www.hosp.jihs.go.jp/index.html