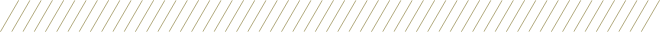横浜市立大学附属病院の
断らない救急医療
消防局と連携し
”All Yokohama”で地域医療を支える
横浜市立大学附属病院は、特定機能病院としての役割を担うと同時に、救急医療や急患応需にも積極的に取り組んでいます。
遠藤病院長は、救急医療と地域医療の両立について、明確に病院の運営方針として示され、原則全ての救急要請を受け入れが可能となる体制を構築しています。また、高度救命救急センターを有するもう一つの附属病院である市民総合医療センター(以下、市大センター病院)との連携も強みです。
横浜市立大学の附属2病院を始めとする医療と行政、地域が連携して総合的な地域力を発揮
竹内主任教授
横浜市立大学附属病院は特定機能病院ですが、 近年、救急搬送件数が前年比10%増のペースで増加しています。その背景には、コロナ禍における病院全体の意識改革があります。具体的には限りあるベッドを院内連携と地域連携で有効に活用しながら、より多くの患者さんを受け入れることです。コロナ対応では、ECMO(体外式膜型人工肺)が必要な重症患者は市大センター病院の高度救命救急センターが主に受け入れ、人工呼吸が必要な重症呼吸不全患者については当院で受け入れる体制をとり、実際に数多くの患者を受け入れてきました。酸素投与が必要な中等症の方は、地域のコロナ重点医療機関協力病院が診療し、悪化した場合には当院へ転院するという役割分担です。
こうした経験を通じて、当院の救急医療に対するスタンスが一歩前進し、救急搬送件数の増加につながりました。
古屋氏
横浜市には約377万人が暮らし、9か所の救命救急センターがあります。2024年中の横浜市の救急件数は25万6000件を超え、過去最多を記録しました。これは1日あたり701件、つまり2分3秒に1回のペースで救急要請がある計算です。横浜市消防局では、重症患者は市大センター病院を中心とする三次救急病院へ、それ以外の患者は症状や緊急度に応じて、二次救急病院や貴院等へ搬送する体制を構築しています。
救急体制の強化には、病院と消防が密接に連携し、患者が行き場を失わない仕組みが不可欠です。私は2024年3月まで横浜市で救急部長を務めましたが、コロナ禍では救急車が長時間搬送先を見つけられずに滞留する「スタック」が頻発しました。
この課題を解決するためには、横浜市立大学の附属2病院を始めとした地域全体の総合的な医療連携体制の強化が必要でした。
竹内主任教授
総合的な『地域力』は横浜市の救急の特徴です。例えば、東京オリンピックの医療体制においても、会場ごとにそれぞれ横浜市立大学の附属2病院や各病院単位で受け持つのではなく、横浜が会場となった野球・サッカー・ソフトボール競技については、『病院・行政・消防』が一つの医療救護委員会を組織して『All Yokohama』で対応しました。この対応は、横浜マラソンやアフリカ開発会議、ワールドカップといったビッグイベントにおける医療救護体制でも同様です。
このような体制があったからこそ、2020年2月ダイヤモンド・プリンセス号が横浜に入港した際も横浜市立大学の附属2病院が率先して対応し、船内から出たPCR陽性の約700名の患者を、重症度により搬送先を分散させることで、医療崩壊を起こすことなく乗り越えることがきました。
遠藤病院長のリーダーシップで救急患者の受け入れを促進
竹内主任教授
横浜市立大学の附属2病院は、それぞれ異なる性質を持ちます。市大センター病院には高度救命救急センターがあり、約30名のスタッフが24時間365日体制で緊急手術から術後管理まで自分達で管理をしています。
一方、当院は特定機能病院として、当院でしか治療ができない患者さんが多くいます。救急については専門的な診療科との連携が不可欠で、救急医がまず全身状態の評価したあとに専門診療科に引き継ぐ症例も多くなっています。地域の先生方の要請にも応えられるよう地域連携課と連携しながら、必要に応じて他院への転院調整や紹介も行います。コロナ禍にあった2020年頃から、急性期や回復期を担う病院との連携体制はより強固になっています。
古屋氏
消防も病院との連携強化に努めています。コロナ禍では119番の要請が急増し、救急車がスタックする事態に陥りました。横浜市では、国が示す「整備指針」に付加して、昼間の人口動態や高齢者の割合を考慮しながら、人員や救急車の増強を決定しています。
現在、87隊の救急隊で市民を支えており、年末年始やインフルエンザの流行時などは必要に応じて90隊以上に増隊する体制を整えています。
川の流れに例えれば、救急車の搬送を上流とすると、病院での受け入れが下流です。下流がボトルネックになると川は溢れてしまいます。救急車のスタックが起きない流れを維持するには、貴院のような、速やかに応需いただく連携構築は必要不可欠です。

竹内主任教授
市民に貢献するためには、今すぐ治療を必要としている救急患者さんの受け入れは重要です。一方で、特定機能病院として待機的入院や手術予定の患者さんへの対応も同じく重要となります。
これを両立させるためには、各部署・部門が組織横断的に連携し、限りあるベッドをより効率よく運用させることが重要で、紹介患者さんのスムーズな受入体制の向上をすすめています。
毎日の病院長ミーティングでは、救急患者の不応需事案が報告され、課題を分析し改善を図っています。たとえば、退院調整の工夫や地域連携を強化して、受け入れ可能な病院を増やす取り組みを進めています。
古屋氏
消防でも、救急件数の増加に対応するため、救急活動のDX化を進めています。横浜市救急業務検討委員会には竹内先生にもご参加いただき、効率化のための答申を提出しました。従来、救急隊は病院搬送の際、受け入れ先が見つかるまで携帯電話で複数の病院に問い合わせをする必要がありましたが、近い将来、患者情報を迅速に医師へ共有できるシステムを導入する予定です。
これにより、病院への連絡時間、帰隊後の報告事務など一連の活動時間が短縮され、限られた救急資源の有効活用を目指しています。
横浜市全体の救急医療の充実を目指して
竹内主任教授
私は横浜市メディカルコントロール協議会の会長として、救急医療体制をより適切に機能させるための方針策定や、消防と協力しながら救急隊の患者さん評価の精度向上を目指しています。救急隊が患者の状態を基に迅速に病院を選定できるプロトコルが確立されており、横浜市立大学の附属2病院でも可能な限り多くの患者さんを受け入れています
古屋氏
横浜市の救急隊員は、定期人事異動により市内各区の地域特性を把握しています。例えば、高齢者が多い地域で病院が限られている場合、区域外搬送を検討するなど、地域ごとの実情を考慮した対応を行っています。救急隊が最初に連絡した病院が迅速に受け入れてくれることが理想的であり、その点で横浜市立大学附属病院の全例応需を原則とする積極的な取り組みは大変助かっています。
竹内主任教授
救急医療や急患対応に携わる医師にとっては自院だけでなく、地域全体の俯瞰的な視野を持つことも重要です。
コロナ禍の初期には、医療現場に恐怖感や不安が広がりましたが、それを乗り越えるには「自分たちがやらなければ、誰が地域を支えるのか」といった強い使命感を持つことが必要でした。
今後も、医療現場の負担を軽減しながら、横浜市全体の救急医療の質を向上させる取り組みを続けていきたいと考えています。

地域の先生や病院間で連携して、よりよい医療を
竹内主任教授
横浜市立大学の附属2病院は、それぞれ異なる役割を担いながら連携し、地域医療に貢献しています。市大センター病院の高度救命救急センターが満床の際は当院で入院させたり、またその逆のケースもあります。両病院がベッドの空き状況を日頃から共有し、スムーズな対応や連携が可能になりました。
今後は、手術室の相互活用や専門医の派遣を含めた、より高度な連携体制を構築していくことが課題です。
古屋氏
横浜市立大学附属病院との連携強化も重要ですが、現在は、救急車の適正な利用につなげるため「あんしん救急」にも力を入れています。例えば、救急安心センター事業「#7119」では、医師や看護師が電話相談を行い、不急な救急搬送を減らす取り組みを行っています。子育て世代へSNSでの情報発信に加え、高齢者向けにリーフレットを配布し、在宅医療関係者とも連携を強化しています。
救急搬送の最適化と地域医療の充実を両輪として進めていくことで、高度医療が必要な患者さんは貴院や市大センター病院にお願いするなど、必要とされる医療に適切に繋げるようにしていくことも大切です。
竹内主任教授
近年、当院に搬送される患者さんの高齢化が進み、複数疾患を抱える患者さんが増えています。今後は、病院内での対応にとどまらず、ACP(Advance Care Planning)の観点から、開業医の先生方とこれまで以上に連携しながら、地域全体で医療を提供する体制が求められます。
現在は病院間での転院が主流ですが、今後は急性期治療を担った後、できるだけ早い段階で在宅医療や地域の先生方へバトンタッチできる仕組みを整えられればと考えます。例えば、高齢者がインフルエンザによる脱水で入院した際、転院が難しいケースでも、訪問診療や訪問看護を活用できれば、自宅での療養が可能になります。
また当院では、現場救急隊からの応需依頼だけでなく、地域医療機関からの急患応需の相談にも専用ホットラインを通じて対応しています。地域の先生方と連携し、病院と地域が役割を分担することで、より適切で持続可能な医療の提供を目指していきたいと考えています。

横浜市立大学附属病院
『市民が心から頼れる病院』の理念のもと、『高度かつ安全な医療』の提供とともに、 神奈川県にある唯一の公的医育機関附属病院として、『質の高い医療人を養成』することを使命に診療。
-
所在地
神奈川県横浜市金沢区福浦3丁目9
-
病床数
671床 (一般:612床、精神:23床、結核:16床、臨床試験専用病床:20床)
-
URL
https://www.yokohama-cu.ac.jp/fukuhp/