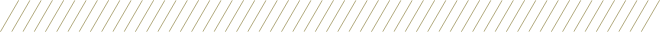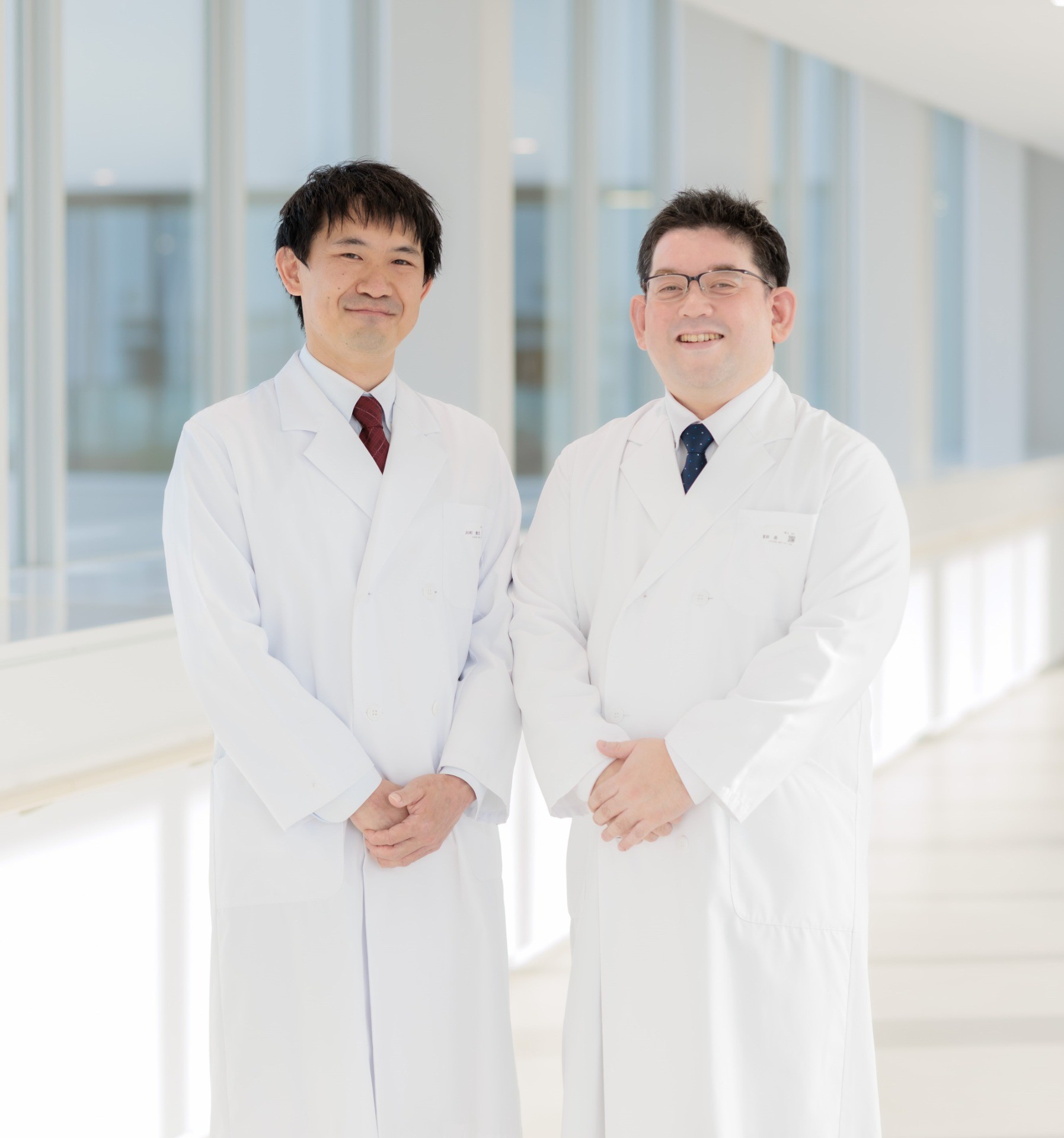緊急手術をチームワークで受け入れ、
合併症リスク低減・ロボット支援下手術に取り組む
浜松医療センター消化器外科は、情報共有やチームワークによって、多くの緊急手術を受け入れる体制です。高齢者に対する大腸がんの手術では、合併症のリスクを下げるためプレリハビリテーションや術中ICG蛍光観察を行っています。他科と連携して患者さんに適した治療法を検討し、ロボット支援下手術にも取り組んでいます。内痔核外来では、大腸がんのスクリーニングが可能です。
プレリハビリテーション、術中ICG蛍光観察で合併症リスクを下げる
原田医長:消化器外科で治療している大腸疾患で一番多いのは、大腸がんです。大腸がんの症例では近年、若年化と高齢化がみられます。生活習慣の欧米化で多くの若い方が大腸がんに罹患する一方、元気な高齢者が増え、手術適応になる方も多くなりました。高齢者は合併症のリスクが高く、対策としてプレリハビリテーションを行っています。プレリハビリテーションは、手術の前に歩行訓練や自宅での生活指導を他科・多職種連携で行う取り組みです。術前に歩行能力や筋力が改善されていると術後の回復が早くなり、肺炎などの合併症が減ると報告されています。
川村医長:消化管の手術では、手術の精度を上げるため、術中ICG蛍光観察を導入しています。大腸がんの手術における術中ICG蛍光観察は、手術中にインドシアニングリーン(ICG)を静脈内投与し、近赤外励起光の照射によって近赤外蛍光を画像化して、腸管の血流を見る方法です。手術室を暗くして、腹腔鏡をICGモードに切り替えて観察します。高齢者は、糖尿病をはじめとする基礎疾患がある方が多く、腸管の血流が低下して縫合不全を生じるリスクがあります。大腸がんの手術で縫合不全が起きると人工肛門が必要になる可能性があるため、切除する部位の血流をリアルタイムに確認できる術中ICG蛍光観察は有効です。ICGは、乳がんのリンパ節への転移や肝機能を調べる検査にも使われてきました。大腸がんの術中ICG蛍光観察は保険適用になり、当院でもヨードアレルギーや腎機能障害がない方には、広く使っています。
ロボット支援下手術を導入
川村医長:当院では2023年8月より、ダビンチによるロボット支援下手術を導入しました。ロボット支援下手術は、2018年4月に直腸がん、2022年4月から結腸がんで保険収載され、現在はすべての大腸がんで保険診療が可能です。日本ではロボット支援下手術の長期成績が出ていませんが、短期間の成績では腹腔鏡に比べて開腹移行率が低く、神経損傷や合併症が少ない傾向があります。術者の慣れが求められますが、ロボットは人間の手と違ってブレがなく、骨盤内のような狭い空間で微細な動きをするのに適しています。特に直腸は、ロボット支援下の方が腹腔鏡より手術しやすい部位です。
ロボット支援下手術は、腹腔鏡手術と比較して同じくらい低侵襲で合併症が起きにくい方法ですが、本格導入になってから日が浅いため手術時間が延長することが指摘されています。

体力的に手術時間を短くしたい高齢者の方には腹腔鏡手術を選ぶといった見極めをして、それぞれの患者さんの状態を考慮し、より適した手術法を決定しています。腹腔鏡手術では術者と助手、カメラアシスタントの3人が必要ですが、ロボット支援下手術では、術者が手術部位の視野の確保も行い、主導的に手術できます。働き方改革が始まり、20年後には消化器外科医が今の人数の半分になるとされる時代に、少ない人数の医師で同じ水準の手術ができるのはメリットです。
原田医長:消化器外科では、消化器内科や放射線診断科とも連携して治療法を決定する方針です。また、外科のカンファレンスを週に3回開き、慎重に手術について検討しています。さらに術後、病理の先生も交えてのカンファレンスも行っています。
内痔核外来では、直腸がんのスクリーニングも可能
原田医長:当科では、消化器内科の便潜血外来と並列して、内痔核外来を始めました。肛門疾患のほとんどは良性疾患ですが、直腸がんが隠れているケースもあります。内痔核外来は、大腸疾患のスクリーニングにも対応しています。肛門の悩みは相談しにくく、長く悩まれている患者さんが多いのが特徴です。肛門からの出血といった症状の患者さんがいらっしゃれば、ぜひご紹介ください。
情報の「共有」とチームワークで多くの緊急手術を可能に
原田医長:当科は緊急手術の症例数が多く、大腸では大腸穿孔、絞扼性腸閉塞やヘルニア嵌頓、急性虫垂炎、外傷が主な対象疾患です。大腸穿孔には良性と悪性の原因があり、緊急性や命に関わるかどうかは症例によって異なります。穿孔はがんで起きる場合のほか、憩室で壁が薄くなって生じるケースがあります。
腸閉塞やヘルニアで腸がねじれて血の巡りが悪くなり、壊死する可能性があるケースは緊急手術の適応です。腸のねじれを解除して傷んだ部分を除去しないと、腹膜炎で全身状態が悪くなります。腸に血流があるか放射線診断科と一緒に診て、消化器外科医が手術の要否を判断しています。急性虫垂炎にも緊急手術と経過観察の見極めが必要です。
川村医長:大腸穿孔は以前、手術をしても30%の致死率でしたが、抗生剤治療や集中治療室での全身管理の進歩によって約10%程度に成績が向上しました。大腸穿孔は高齢者に多く、がんや便の溜まりすぎが主な原因です。高齢者は予備能が低く、早急な対応と術後管理が求められます。浜松医療センターでは2024年に新病棟が完成し、ICUのスペースが広がりました。常勤の集中治療科医が、リスクの高い患者さんの術後管理を担当できる体制になっています。
原田医長:緊急手術のほとんどが時間外での対応です。当科では「共有」をキーワードに、チーム全体で働き方改革に取り組み、安定して手術を受けられるようにしています。指導医と専攻医では、立場が違うため配慮も必要です。若い先生には緊急手術が必要か、様子を見るかの判断が難しいため、相談しやすいようにサポートしています。
原田医長:救急対応当番を決め、手術が忙しいときは外来と同時の場合もありますが、日勤帯でもなるべく1人は救急に対応しています。救急医を介さず救急車から直接、当番の消化器外科医が連絡を受け、手術室が空いていればすぐに入室できる体制です。1人では手術できないので、アプリ等による情報共有で、手術に入れる医師を見つける工夫も始めました。

気軽にお腹の症状がある患者さんのご紹介を
原田医長:私は家族が病院にかかることが多く、医師を志しました。大学を卒業する頃、手術室のピリッとした空気が好きで、外科を選んだ記憶があります。診療科は迷いましたが、手術ですっきり治る患者さんをよく診た消化器外科に決めました。
川村医長:小学生のときにドラマ『振り返れば奴がいる』を観て、消化器外科医に憧れました。大学生で何回か骨折して整形外科も考えましたが、緊急手術が多く、外科の王道というイメージがあった消化器外科を選んでいます。がんのように命にかかわる病気を治療し、患者さんと話す医師になりたいと思っていました。

原田医長:地域の先生方が消化器の疾患を疑われた場合、消化器外科に気楽にご相談ください。消化器内科と消化器外科のどちらに送るべきか迷うと聞きますが、消化器内科とも連携してカンファレンスを行い、患者さんに適した治療を行っています。腹膜炎を起こすような腹部の所見として、触診でお腹が硬いというのは、地域の先生方もご存知だかと思いますが、本当に硬いお腹の触診に慣れていないと、診断は難しいかもしれません。お腹の痛みは波があって消えることがあり、重症の場合でも必ずどんどん痛くなるわけではないのです。大腸がんは一般的に症状がなく、穿孔して気がつくケースがあります。ご心配な患者さんがいらっしゃれば、ぜひご紹介ください。
川村医長:虫垂炎の疑いで来られた患者さんが、虫垂炎ではなく胃腸炎だったというケースはよくあります。手術が必要かどうかの判断は、血液検査とお腹の所見だけでは難しく、CTも必要です。地域の先生には、腹痛の患者さんがいらっしゃれば気軽に送っていただければ幸いです。
浜松医療センター
静岡県西部地区を診療圏とする高度総合医療機関であり、地域医療支援病院、災害拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、地域周産母子医療センター、アレルギー疾患医療拠点病院、日本脳卒中学会一次脳卒中センター、そしてゲノム医療連携病院の責を担っている。
-
所在地
静岡県浜松市中央区富塚町328
-
病床数
606床
-
URL
https://www.hmedc.or.jp/